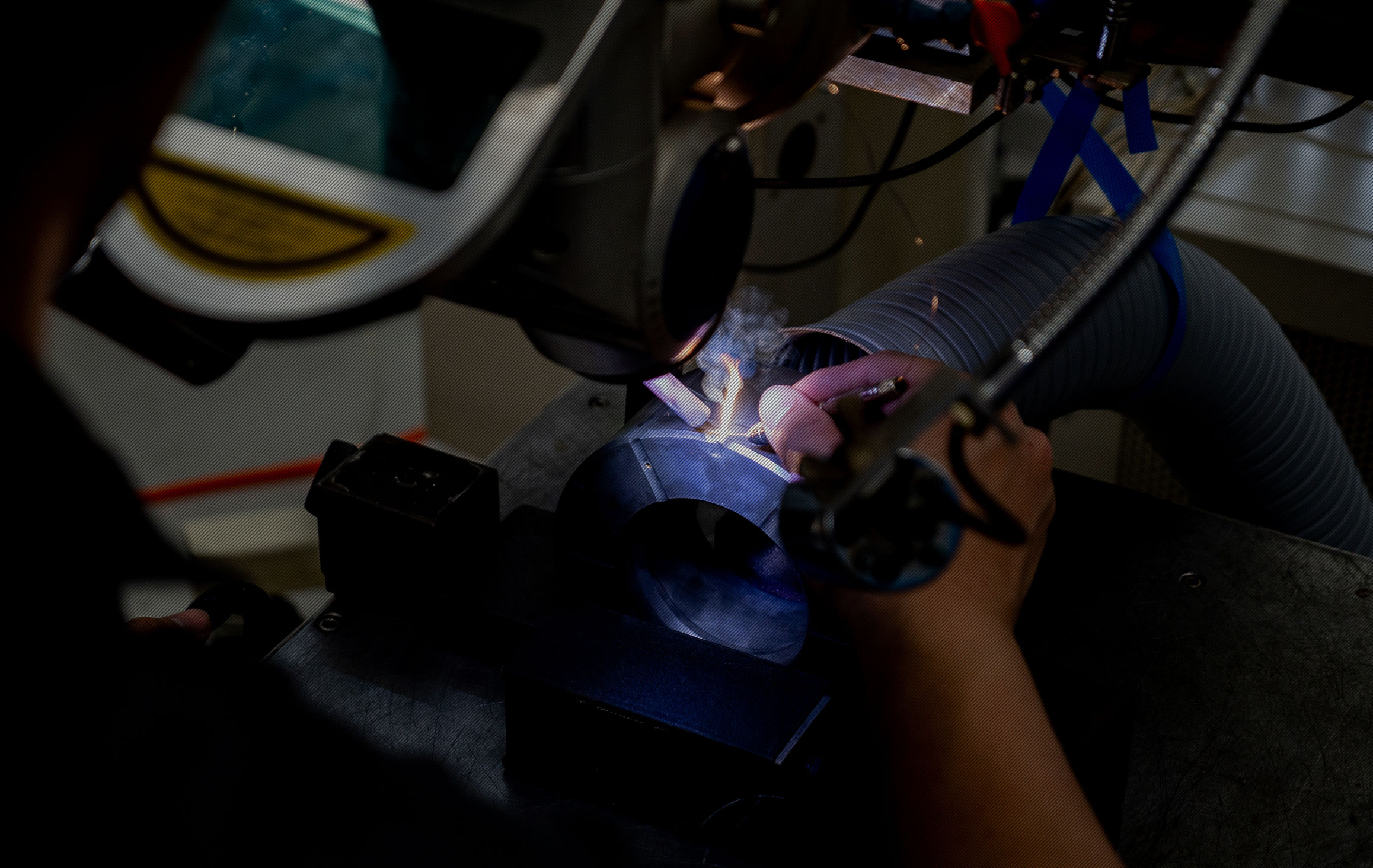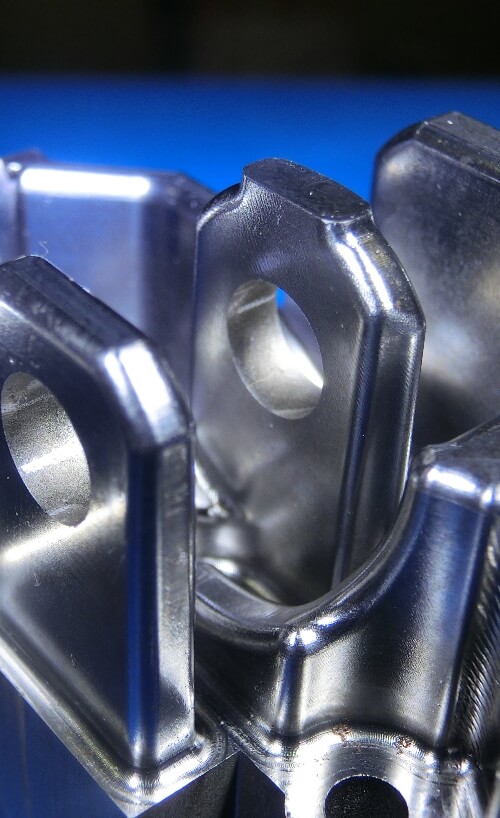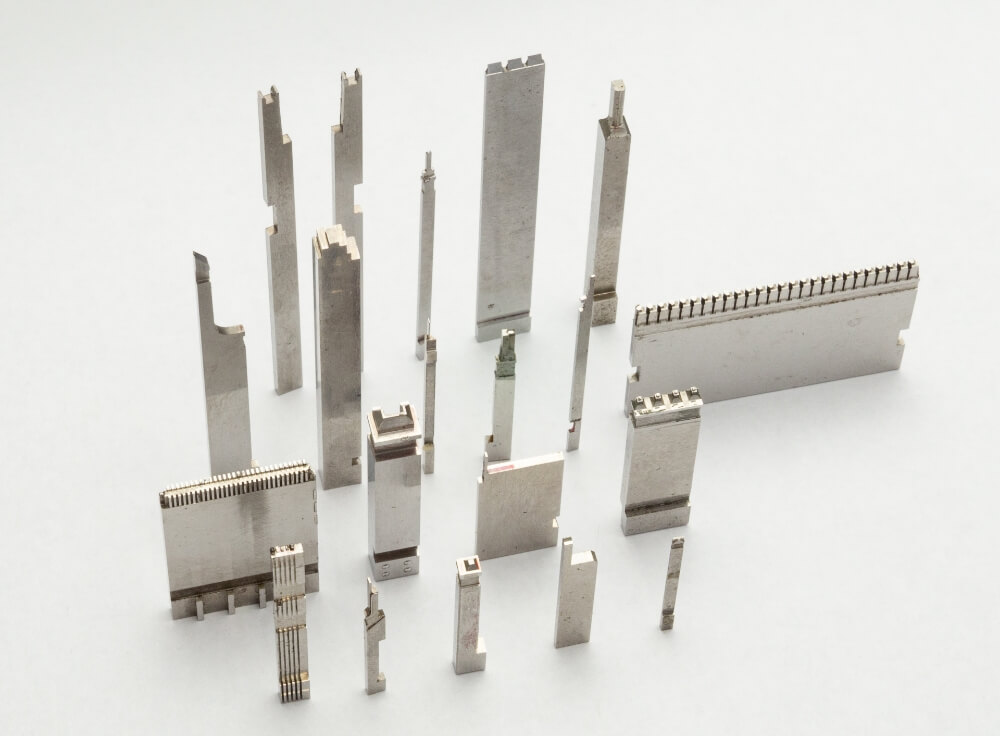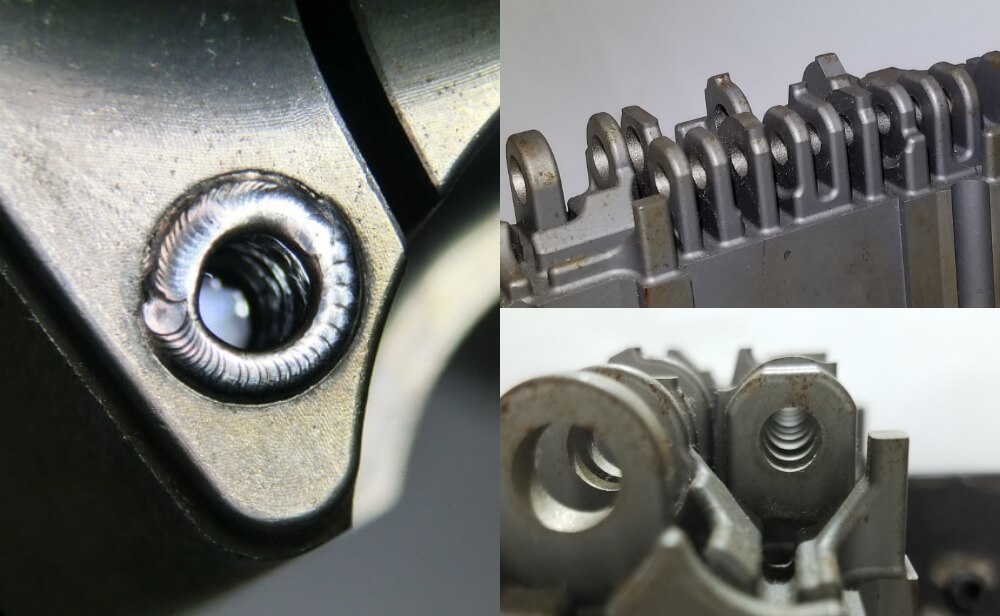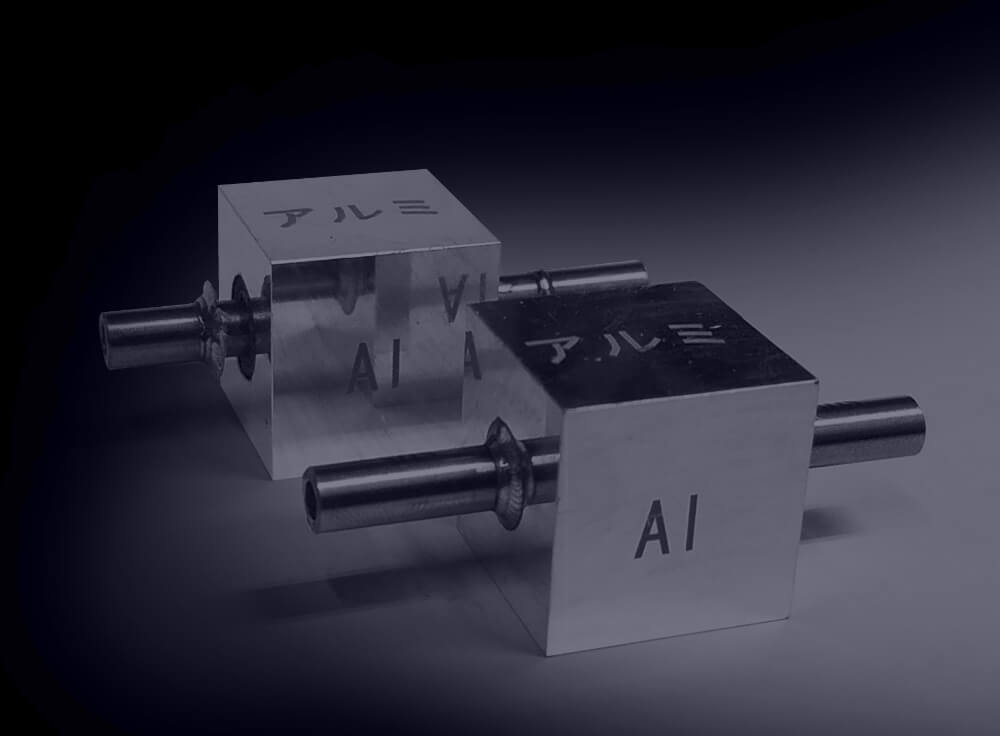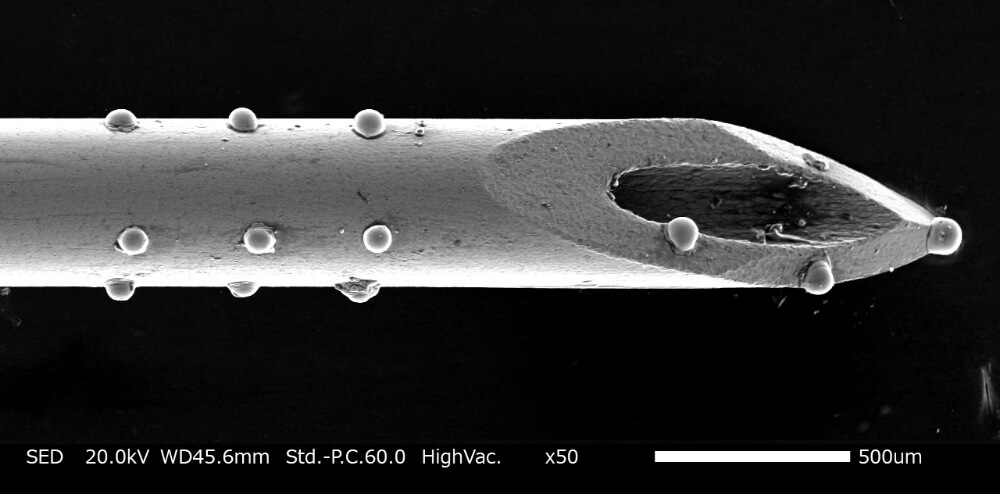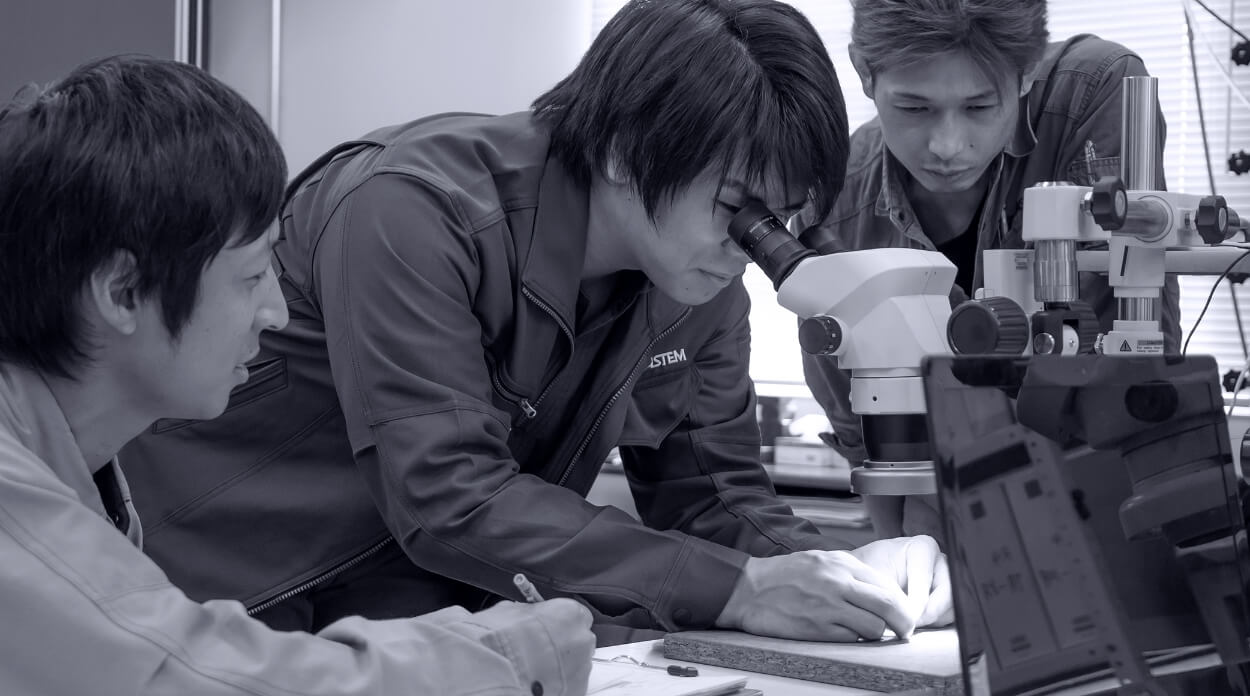技術を高め、己を高め お客様、そして社会へ 貢献する企業へ
選ばれる理由
業界では最大数の設備を有し、
微細な溶接から大量盛りまで
迅速な対応が可能
事業発足以来、現在までに累計15万件を超える受注実績があり、安心してご利用いただいております。特に新規お客様のリピーター率は87%超と高い評価をいただいております。
また、レーザー溶接に関わる研究開発、既存事業の高度化など協力機関(産学)連携により幅広く展開、お客様に必要な製品、情報などをご提供しています。
金型肉盛り BUILD-UP WELDING
CONTACT お問い合わせ
キャステムへのお問い合わせはお電話またはメールフォームにて承ります。必要事項をご入力いただき送信してください。折り返しメールまたはお電話でご連絡差し上げます。
※お急ぎの場合はお電話でお願いいたします。
お電話でのお問い合わせ
076-465-3582
[受付時間]月曜〜金曜 8:30〜17:20
WEBからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム
オンラインミーティングについて
ZOOM・Microsoft Teamsでの
オンラインミーティングについて